



2025年9月1日
『現代インプラントの父』と称されるスウェーデンのブローネマルク博士(1929-2014)がインプラントの臨床応用を開始してから、まもなく60年を迎えようとしています。
その間、世界中のインプラント外科医が様々な手術法を開発し、今やインプラント治療はブリッジや義歯に代わる抜歯後の第一選択肢として広く認知されるようになりました。
と同時に、世界中のインプラントメーカーは、インプラント本体および関連部品の開発・改良にしのぎを削ってきました。
開発目標の2本の柱は、1つが、「インプラント周囲により早く、より多くの新生骨を誘導・結合させること」、そしてもう1つは、「インプラント周囲にできた骨を減少させないこと」でした。
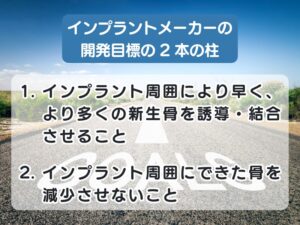
そこで、今回はインプラント周囲骨の減少(吸収)についての基礎的なお話をします。
インプラントの原理は、ドリルで穴をあけた顎骨にネジ形状の金属製(チタン)のインプラントを埋め込み、チタンと骨が結合した後にそれを土台として人工歯を連結することです。
以前の歯のコラム「インプラント治療の正確性」でもご紹介したように、インプラントは天然歯の歯根に相当します。
歯根周囲の骨が吸収する2大原因は力(歯ぎしり等の自分の意思でコントロールできない過大な力)と感染(歯周病菌による細菌感染)ですが、このことはインプラントにもあてはまります。

歯ブラシ等のTVコマーシャルでは、歯周病に関連した『歯周ポケット』という言葉を耳にします。
歯周ポケットとは、もともと歯の周囲に存在する深さ1~2mm程度の隙間(歯肉と歯の表面がくっついていない溝のような隙間)が病的に深くなった状態です。
歯周ポケットが深くなればなるほど日常的な歯磨きだけでは対処できなくなり、歯周ポケット内の歯周病菌数は増加し、歯肉の炎症・腫れと周囲骨の病的吸収が進行します。

骨吸収が進行すれば歯周ポケットはさらに深くなるという負のスパイラルに陥ります。
そしてこのスパイラルを増長するのが歯ぎしり等の過大な力や糖尿病等の免疫系の異常です。
また、顎骨に埋め込んだインプラントに人工歯を連結すると、比較的早期にインプラント周囲に1.5mm程度の骨吸収(皿状骨吸収)が生じ、それはシステム上避けることができない(生体の防御機構)と考えられてきました。
皿状骨吸収そのものは進行性ではないため問題ありませんが、歯磨き不足等の状況下では進行性の病的吸収から、インプラント周囲ポケットの深化へ移行するきっかけになり得ます。
ある時、米国の歯科医師(Dr.ラザーラ)が在庫不足を理由にインプラント直径よりも小さな連結部の人工歯を装着したところ、皿状骨吸収が生じていないことを偶然発見しました。
この発見を契機に開発されたシステムがプラットフォームスイッチング(X線写真でインプラント上部連結部に段差の設定)です。

旧連結型インプラント

新連結型インプラント
当院では年前からプラットフォームスイッチング・システムのインプラントに変更していますが、従来の段差のない連結システムに比べて良好な結果を実感しています。
今後も、効果の期待できる新技術を積極的に取り入れていきたいと考えています。

お口のトラブルやお悩みなど、気になることがありましたらお気軽にご相談ください。